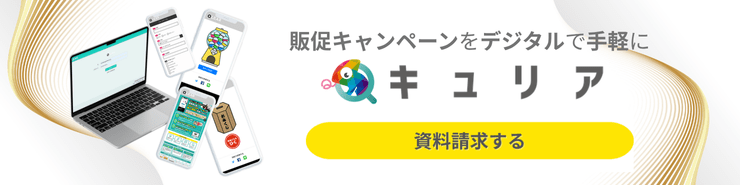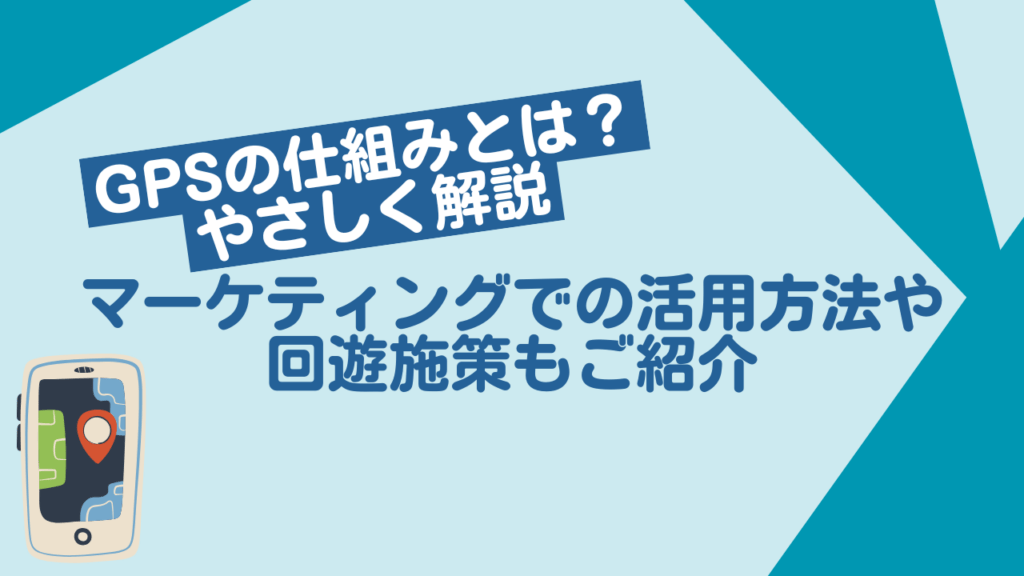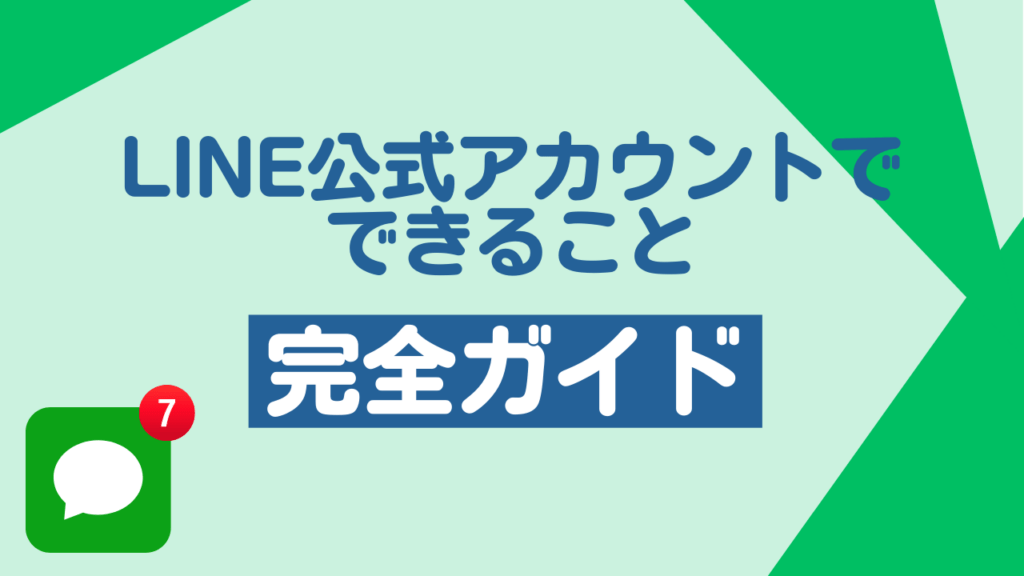2025年11月7日
二段階抽選とは?参加率を高める仕組みと活用事例を徹底解説
二段階抽選とは?参加率を高める仕組みと活用事例を徹底解説
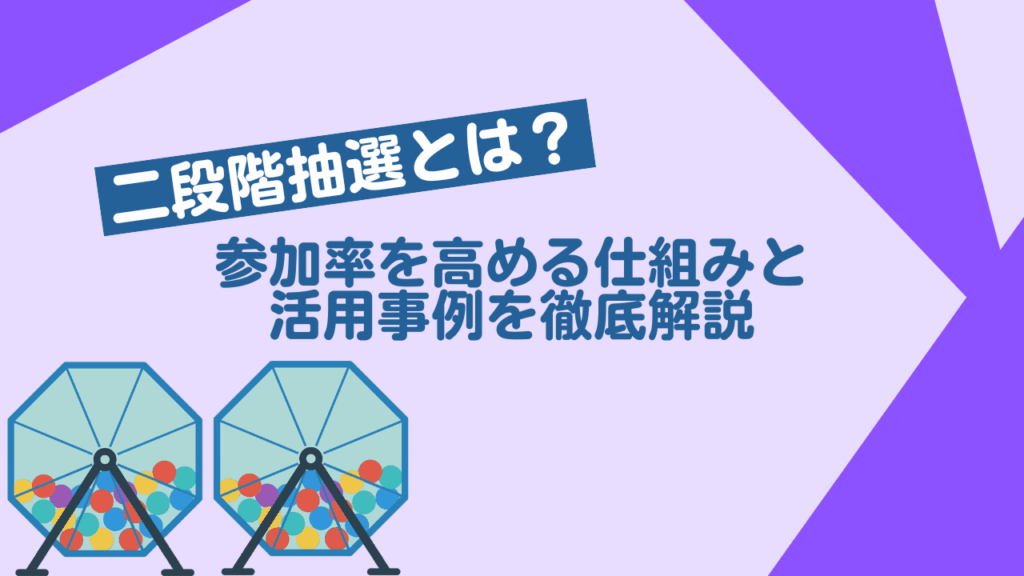
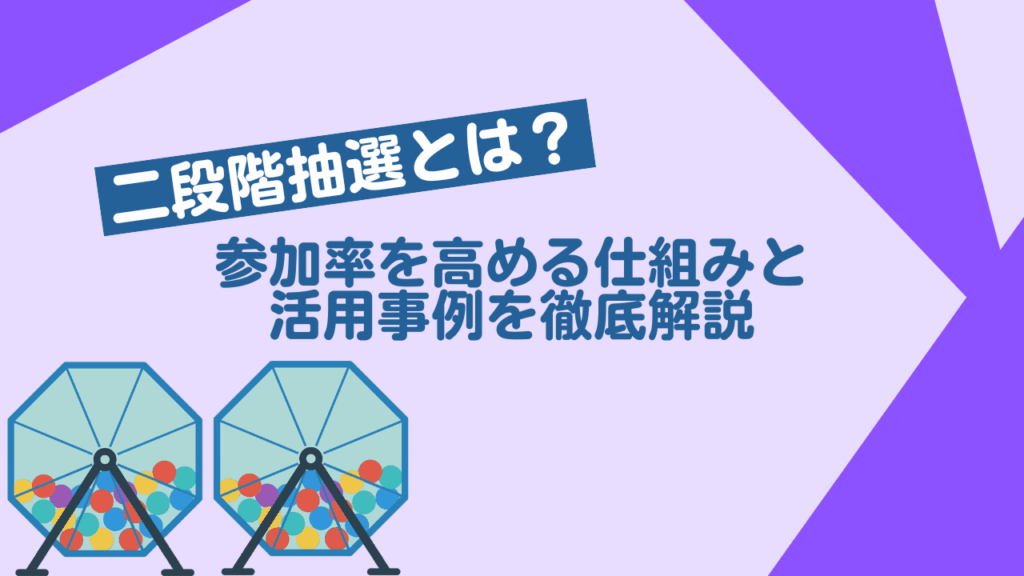
1. はじめに
イベントや販促キャンペーンにおいて、抽選コンテンツは参加者の関心を引き、
集客や売上に貢献する施策として広く活用されています。
しかし、参加者の人数や景品の消化状況を正確に予測するのは難しく、
抽選の設定に頭を悩ませる企画担当者も多いのではないでしょうか。
特に商業施設や住宅展示場、自治体のイベントなどでは、「景品が早々に尽きてしまった」「逆に大量に余ってしまった」
といった問題が頻繁に発生します。
そこで近年注目を集めているのが「二段階抽選」という仕組みです。
この記事では、二段階抽選の基本的な定義から、具体的な活用シーン、導入メリットや注意点までを詳しく解説します。
ノーコードで手軽に二段階抽選を実現できるツール「キュリア」についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
2.二段階抽選とは?
■ 基本的な定義
二段階抽選とは、あらかじめ設定した第一段階の抽選設定(例:当たり本数100本)が終了した後、
自動的に第二段階の設定(例:すべてハズレなど)に切り替わる仕組みのことを指します。
つまり、くじが予定数を引かれる前に終了したり、景品がすべて配布されたりした場合でも、
抽選システムを継続して運用できる柔軟な設計です。
従来のアナログ抽選では、景品が尽きた時点で抽選を終了するか、急遽代替景品を用意する必要がありました。
しかし、二段階抽選を採用することで、システムが自動的に次のフェーズへ移行するため、運営側の負担が大幅に軽減されます。
■ よくある誤解との違い
一見すると「当選者にだけプレミアムな抽選を提供するダブルチャンス」のようなイメージを持たれることもありますが、
それとは異なります。
二段階抽選は「抽選全体のフェーズが切り替わる」ものであり、参加条件や景品の内容自体がシステム的に変化します。
ダブルチャンスが「当選者への追加特典」であるのに対し、二段階抽選は「全参加者に対する抽選条件の段階的変更」
という点で大きく異なるのです。
■ 二段階抽選の仕組みを図で理解する
二段階抽選の流れを整理すると、以下のようになります。
【第一段階】
- ・参加者数:0〜200人
- ・当選設定:100本の当たり/100本のハズレ(当選確率50%)
- ・状態:景品在庫あり
【自動切り替えポイント】
- ・条件:200人が参加完了
【第二段階】
- ・参加者数:201人以降
- ・当選設定:すべてハズレ または 別の景品に切り替え
- ・状態:メイン景品は配布終了
このように、用意した第一段階のくじがすべて出切った時点で、システムが自動的に第二段階の抽選条件に変更されます。
運営者は常に抽選状況を監視する必要がなくなり、イベント運営に集中できるのです。
3.二段階抽選が活用されるシーン
■ 抽選参加者数の予測が難しいとき
たとえば、1,000本のくじを用意し、その中に当たりを100本設定したとします。
この場合、参加者が1,000人に達すれば理論上100本の当たりが放出されます。
しかし、実際には200本しかくじが引かれなかった場合、200本すべてがハズレである可能性もあります。
このようなリスクを防ぐために、第一段階では200本の抽選に対して100本の当たりを設定し、
終了後の第二段階では残りの800本をすべてハズレに設定するという運用が可能になります。
具体的な活用例
商業施設での週末イベントを想定してみましょう。
通常の週末であれば500人程度の来場が見込めますが、天候や周辺イベントの影響で200人程度になることもあります。
第一段階で「200人分の抽選に50個の景品を配分」と設定しておけば、来場者が少ない場合でも適切に景品を配布でき、
参加者の満足度を維持できます。
■ 先着景品配布をしたいとき
景品を先着順で配布したい場合にも二段階抽選は有効です。
第一段階では必ず何かしらの景品が当たる抽選を設定し、用意したくじがすべて出切ったタイミングで、
第二段階としてすべてハズレに切り替えることができます。
また、第二段階でも新たに別の景品を設定することも可能です。
実践的な運用パターン
住宅展示場のキャンペーンでは、以下のような設定が効果的でしょう。
- ・第一段階(設定した200本のくじ):高級家電や商品券などのメイン景品
- ・第二段階(200本のくじが出切った後):参加賞として飲料やお菓子などの小さな景品
このように段階的に景品を変更することで、「早く参加するメリット」を明確に打ち出しつつ、
後から参加した方にも何らかの特典を提供できます。
■ 参加者層によって景品を変えたいとき
一日を通じて開催されるイベントでは、参加者層が変わることがあります。
二段階抽選を活用すれば、一段階目は家族向けの景品を多く用意し、
二段階目はビジネスパーソン向けの景品を多く用意するといった柔軟な設定が可能です。
活用シーン
長時間開催される展示会やフェスティバルでは、第一段階で限定数の高額景品(先着500名など)を設定し、
くじがすべて出切った後の第二段階ではすべての来場者が参加できる参加賞に切り替えることで、
イベント全体を通じて抽選の継続が可能になります。
用意したくじを出し切ることが切り替えのポイントとなるため、運営側は景品の在庫状況を常に把握できます。
■ 予算管理を厳密に行いたいとき
広告代理店の企画担当者にとって、クライアントの予算内で最大限の効果を出すことは重要な課題です。
二段階抽選を活用すれば、予算の消化ペースをコントロールしながら、参加者の満足度を維持できます。
予算管理の実例
総予算50万円のキャンペーンで、1等(5万円相当)×5本、2等(1万円相当)×20本、3等(3,000円相当)×50本を用意したとします。
第一段階で上記の景品を配布し、用意したくじがすべて出切った時点で第二段階として「デジタルクーポン(原価ほぼゼロ)」
に切り替えれば、予算超過のリスクを回避しつつ、すべての参加者に何らかの特典を提供できるのです。
4.二段階抽選のメリットと注意点
■ メリット
1.抽選の予算消化を柔軟に管理できる
二段階抽選の最大のメリットは、予算管理の柔軟性です。
第一段階で高額景品を配布し、第二段階で低額景品や参加賞に切り替えることで、
予算の範囲内で最大限の参加者にリーチできます。
特に、クライアントから厳密な予算管理を求められる広告代理店の企画担当者にとって、
この機能は非常に心強い味方となるでしょう。
2.当選者ゼロなどの不測の事態を防げる
従来の抽選では、確率設定の誤りや参加者数の読み違いにより「誰も当たらない」という事態が発生することがありました。
二段階抽選では、第一段階で確実に景品を配布し、第二段階で調整を行うため、このようなトラブルを未然に防げます。
参加者からの「全然当たらない」というクレームも大幅に減少するはずです。
3.抽選の持続性を確保しつつ、景品の在庫管理がしやすい
イベントやキャンペーンの期間中、常に抽選を継続できることは参加者の満足度向上につながります。
「景品が尽きたので抽選終了」という事態を避けられるため、イベント全体の盛り上がりを維持できるでしょう。
また、在庫管理の観点からも、第一段階で確実に景品を消化し、第二段階で残数を調整できるため、
余剰在庫や不足のリスクを最小限に抑えられます。
4.景品切れによるクレームリスクを最小限に抑えられる
「せっかく来たのに景品がない」というクレームは、イベント運営において最も避けたい事態の一つです。
二段階抽選では、メイン景品が尽きた後も参加賞や別の景品を用意することで、すべての参加者に何らかの特典を提供できます。
これにより、クレームの発生を大幅に抑制し、ブランドイメージの低下を防げるのです。
5.データ分析による次回施策の改善
デジタル抽選システムを使った二段階抽選では、各段階での参加者数、当選率、景品の人気度などのデータを詳細に記録できます。
このデータを分析することで、次回のキャンペーンでは「第一段階の景品数をもう少し増やすべきか」
「切り替えタイミングを早めるべきか」といった改善点が明確になるでしょう。
■ 注意点
1.システム側での切り替え条件を明確に設定しておくこと
切り替え条件が曖昧だと、運営側の判断ミスやシステムエラーが発生しやすくなります。
二段階抽選では、用意した第一段階のくじがすべて出切った後に、自動的に第二段階に切り替わるというトリガーが設定されます。
事前に以下の項目を明確に定義しておきましょう。
- ・第一段階のくじの総数
- ・切り替え後の第二段階の抽選内容
- ・切り替え後の通知方法(参加者への告知、運営スタッフへの通知)
特に、複数のスタッフで運営する場合は、切り替え条件を共有し、誰が見ても分かるマニュアルを用意することが重要です。
2.管理者による抽選結果のモニタリングと調整が求められる場合もある
二段階抽選は自動化できる部分が多いものの、予期せぬ事態に備えて管理者によるモニタリングは欠かせません。
例えば、予想以上に参加者が多く、第一段階のくじが早期に出切りそうな場合は、
第二段階の景品内容を調整する必要があるでしょう。
リアルタイムで抽選状況を確認できるダッシュボード機能を持つシステムを選ぶことをおすすめします。
3.法的・倫理的な配慮
抽選キャンペーンを実施する際は、景品表示法や不当景品類及び不当表示防止法(景表法)を遵守する必要があります。
特に、以下の点に注意しましょう。
<景品の上限額>
– 一般懸賞の場合、取引価額が5,000円未満なら取引価額の20倍まで
– 取引価額が5,000円以上なら一律10万円まで
<景品総額>
– 懸賞に係る売上予定総額の2%まで
<抽選条件の明確化(推奨)>
– 商品購入や来店が必要な「クローズド懸賞」か、誰でも参加できる「オープン懸賞」かを明確にすることがトラブル防止につながります
– 参加条件を分かりやすく表示することで、参加者の信頼獲得と不当表示の防止に役立ちます
– なお、オープン懸賞(商品購入や来店を条件としない抽選)の場合は、景品の上限額規制は適用されません
5.二段階抽選を簡単に実現できるツール「キュリア」
ここまで二段階抽選の仕組みやメリットを解説してきましたが、「実際にどうやって実装すればいいの?」
と疑問に思われた方も多いでしょう。
そこでおすすめしたいのが、ノーコードツール「キュリア」です。
■ キュリアとは
キュリアは、スマートフォンを使った抽選コンテンツを誰でも簡単に作成できるノーコードツールです。
プログラミング知識がなくても、直感的な操作だけで本格的なデジタル抽選システムを構築できます。
あらかじめ20種類のコンテンツテンプレートが用意されており、抽選、ガチャ、スロット、ルーレット、スクラッチなどの設定も思いのままに行えます。
■ キュリアで二段階抽選を実現する方法
特に注目すべきは、二段階抽選のような柔軟な抽選フローにも対応可能である点です。
キュリアでは、以下のような設定が簡単に行えます。
- ・第一段階の抽選設定:景品の種類、当選本数、当選確率を自由に設定
- ・切り替え条件の設定:用意した第一段階のくじがすべて出切った時点で自動切り替え
- ・第二段階の抽選設定:第一段階終了後の景品内容や当選確率を変更
これらの設定は、すべて管理画面から直感的に操作できるため、システム開発の知識がない企画担当者でも安心して利用できるでしょう。
■ デザインQRでオリジナリティを演出
さらに、キュリアの特徴的な機能として「背景画像を設定できるQRコード(デザインQR)」があります。
通常のQRコードは白黒の無機質なデザインですが、キュリアのデザインQRでは、企業ロゴやキャンペーンビジュアルを背景に設定できます。
これにより、以下のようなメリットが生まれます。
- ・ブランドイメージの強化:企業やイベントのビジュアルアイデンティティを反映
- ・差別化:他社のキャンペーンとの明確な差別化
- ・詐欺防止:オリジナルデザインにより、偽造QRコードのリスクを軽減
デザインソフトでQRコードに画像を重ねると読み取れなくなりますが、キュリアのデザインQR機能なら、
美しいデザインと確実な読み取り性能を両立できます。
関連記事:デザインQRとは?
■ 効果測定とデータ分析
キャンペーン終了後の効果測定にも対応しており、QRコードのスキャンログや抽選履歴を可視化できるのも大きな魅力です。
具体的には、以下のようなデータを取得・分析できます。
- ・QRコードのスキャン数と時間帯別の推移
- ・抽選参加者数と当選者数の詳細
- ・景品別の人気度と在庫消化率
- ・第一段階と第二段階の切り替えタイミングの妥当性
これらのデータを次回のキャンペーン企画に活かすことで、継続的な改善が可能になります。
関連記事:QRコードの効果測定方法
■ キュリアのその他の便利機能
二段階抽選以外にも、キュリアには以下のような便利な機能が搭載されています。
- ・コンテンツの連携:抽選後にアンケートやクーポン配布へ自動遷移
- ・リアルタイム管理:ダッシュボードで抽選状況をリアルタイムで確認
- ・ログ確認:参加者の行動履歴や抽選結果を詳細に記録・確認可能
- ・即時対応:仕様変更が必要になった場合も、管理画面から即座に調整可能
特に、外注に依頼すると数十万円かかるような仕様変更も、キュリアなら自社で即座に対応できるため、
外注費用の大幅な削減につながります。
ログ確認機能を活用すれば、どの参加者がいつ抽選に参加し、どの景品を獲得したかを詳細に追跡できるため、
不正防止やトラブル発生時の原因究明にも役立ちます。
■ キュリアの導入イメージ
実際にキュリアを活用した二段階抽選の導入イメージをご紹介します。
【商業施設のハロウィンイベント】
商業施設では、ハロウィンイベントで来場者向けのデジタル抽選を実施する際、以下のような設計が可能です。
第一段階では、設定した500本のくじに対してハロウィン限定グッズを景品として設定し、
くじがすべて出切った時点で第二段階として施設内で使える500円クーポンに切り替えます。
このような設計により、早期来場のインセンティブを提供しつつ、後から来場された方にも満足いただける特典を用意することで、イベント全体の満足度向上が期待できます。
さらに、クーポンの利用により施設内の店舗売上向上にもつながる可能性があります。
【住宅展示場の週末キャンペーン】
住宅展示場では、週末ごとに来場者向けの抽選キャンペーンを実施する際、景品管理の効率化が課題となります。
キュリアの二段階抽選機能を導入することで、第一段階で高額景品を配布し、
用意したくじがすべて出切った後の第二段階で参加賞を提供するという、すべての来場者に満足いただける仕組みを構築できます。
また、デザインQRを展示場の各ハウスに設置することで、来場者の回遊性も向上し、滞在時間の延長効果も期待できるでしょう。
6.二段階抽選の設計ポイント
実際に二段階抽選を導入する際、どのような点に注意すべきでしょうか。
ここでは、効果的な二段階抽選を設計するためのポイントを解説します。
■ 参加者数の予測方法
二段階抽選の成功の鍵は、第一段階のくじの本数を適切に設定することです。
そのためには、参加者数の予測が欠かせません。
予測に活用できるデータ:
- ・過去の同様イベントの参加者数
- ・会場のキャパシティと想定滞在時間
- ・天候や周辺イベントの影響
- ・SNSやWEB広告の反響
これらのデータを総合的に分析し、「最低ライン」「通常ライン」「最高ライン」の3パターンで参加者数を想定しておくと良いでしょう。
■ 景品設計の考え方
第一段階と第二段階で提供する景品は、明確に差別化することが重要です。
効果的な景品設計の例
- ・第一段階:高額商品、限定グッズ、体験型の特典など、希少価値の高いもの
- ・第二段階:実用的な日用品、デジタルクーポン、次回割引券など、幅広い層に受け入れられるもの
ただし、第二段階の景品を「ハズレ」と感じさせないよう、一定の価値を持たせることが参加者の満足度維持につながります。
■ 切り替えトリガーの理解
二段階抽選の切り替えトリガーは、用意した第一段階のくじがすべて出切った時点で自動的に第二段階へ移行するという仕組みです。
例えば、第一段階で200本のくじを設定した場合、200人が参加した時点で自動的に第二段階に切り替わります。
このシンプルで明確なトリガー設定により、運営側の負担を最小限に抑えつつ、確実な景品管理が可能になるのです。
■ 告知・コミュニケーション戦略
二段階抽選を成功させるには、参加者への適切な情報提供が不可欠です。
事前告知のポイント
- ・キャンペーンサイトやSNSで二段階抽選の仕組みを分かりやすく説明
- ・第一段階の景品の魅力を前面に押し出し、早期参加を促す
- ・第二段階でも特典があることを明示し、参加ハードルを下げる
当日の運営のポイント
- ・会場内のサイネージやポスターで抽選の状況を可視化
- ・第一段階から第二段階への切り替え時に、参加者へアナウンス
- ・スタッフが抽選の仕組みを正しく理解し、問い合わせに対応できる体制を整備
透明性の高い運営により、参加者の信頼を獲得し、ブランドイメージの向上につなげられます。
7.二段階抽選の想定事例から学ぶ
実際に二段階抽選を活用した施策のイメージをいくつかご紹介します。
■ 自治体の地域活性化イベント(想定事例)
ある自治体では、地域の商店街を盛り上げるため、スタンプラリーと連動した二段階抽選キャンペーンを実施しました。
第一段階では、スタンプラリー完走者に対して設定したくじ100本分で地域特産品を提供し、
くじがすべて出切った後の第二段階では完走者全員に商店街で使える500円クーポンを配布しました。
このような施策により、商店街への来訪者数の増加や、参加者からの「最後まで楽しめた」という好評の声が期待できます。
関連記事:地域活性化を実現する自治体集客について〜事例とノウハウを解説〜
■ スポーツチームのファン感謝デー(想定事例)
あるバスケットボールチームでは、ファン感謝デーで選手のサイン入りグッズが当たる抽選を実施するケースがあります。
第一段階では、会場に早く到着したファン限定で設定した300本のくじからレアグッズを景品に設定し、
くじがすべて出切った後の第二段階では全参加者を対象に選手との記念撮影権を景品とするといった設計が考えられます。
この施策により、開場前からの盛り上がりや、遅れて到着したファンの満足度向上が期待できるでしょう。
関連記事:ファン感謝デーや地域イベントをはじめとしたスポーツイベントの集客アイデア9選!
■ 動物園の来園促進キャンペーン(想定事例)
動物園では、平日の来園者数を増やすため、平日限定の二段階抽選キャンペーンを実施する方法があります。
第一段階では、開園直後に来園した方に対して設定した50本のくじから年間パスポートを景品として設定し、
くじがすべて出切った後の第二段階では平日来園者全員にオリジナルグッズをプレゼントするといった設計です。
このような施策により、平日の来園者数増加や、開園直後の来園促進により園内の混雑分散効果が期待できます。
関連記事:動物園や水族館などの博物館の集客アイデア!成功事例から学ぶイベント企画の秘訣とは?
8.よくある質問(FAQ)
Q1. 二段階抽選とダブルチャンスの違いは何ですか?
二段階抽選は「全参加者に対する抽選条件の段階的変更」であり、ダブルチャンスは「当選者への追加抽選機会の提供」です。
二段階抽選では、第一段階のくじがすべて出切った後、すべての参加者が第二段階の抽選条件に従います。
一方、ダブルチャンスでは、第一抽選で当選した人だけが第二抽選に参加できる仕組みです。
Q2.二段階抽選を実施する際、法的に押さえておくべきポイントは?
二段階抽選を実施する際は、景品表示法を遵守することをポイントとしておさえておきましょう。
景品表示法では、景品の上限額と総額が規制されています。
– 景品の上限額: 取引価額5,000円未満の場合は取引価額の20倍まで、5,000円以上の場合は一律10万円まで
– 景品総額: 懸賞に係る売上予定総額の2%まで
Q3. 第一段階と第二段階で景品の価値に大きな差をつけても良いですか?
差をつけること自体は問題ありませんが、第二段階の参加者が「損をした」と感じないよう配慮が必要です。
第二段階でも一定の価値がある景品を用意することで、参加者全体の満足度を維持できます。
Q4. アナログの抽選でも二段階抽選は実現できますか?
理論上は可能ですが、実務的には非常に煩雑になります。
景品の在庫管理、切り替えタイミングの判断、参加者への告知など、すべて人手で行う必要があるためです。
デジタル抽選システムを活用することで、これらの作業を自動化し、運営負担を大幅に軽減できます。
関連記事:アナログとデジタル、どちらを選ぶべき?抽選・スタンプラリー企画の費用と効果を徹底比較
Q5. 二段階抽選の効果をどのように測定すればよいですか?
デジタル抽選システムを使用している場合、以下の指標を測定できます。
- ・第一段階・第二段階それぞれの参加者数
- ・切り替えタイミングの適切性
- ・景品の消化率と在庫状況
- ・参加者の満足度(アンケート等で取得)
これらのデータを分析することで、次回のキャンペーンに向けた改善点が明確になります。
関連記事:QRコードの効果測定方法
9.まとめ
二段階抽選は、抽選参加者の予測が難しい場合や、景品の先着配布をしたい場合などに有効な仕組みです。
当たりの偏りや景品切れによるトラブルを防ぎながら、参加者の満足度を高める運用が実現できます。
この記事のポイント
- ・二段階抽選は柔軟な抽選設計を可能にする:第一段階と第二段階で抽選条件を変更し、予算管理や在庫管理を最適化できます。
- ・さまざまなシーンで活用可能:参加者数の予測が難しいとき、先着景品を配布したいとき、参加者層に合わせて景品を変えたいときなど、幅広い用途に対応できます。
- ・メリットは多岐にわたる:予算管理の柔軟性、トラブル防止、在庫管理の効率化、クレームリスクの低減など、運営側にとって多くの利点があります。
- ・注意点を押さえた運営が重要:参加者への明確な説明、システム設定の厳密化、リアルタイムモニタリングなど、適切な運営体制を整えることが成功の鍵です。
- ・ノーコードツールで簡単に実現:キュリアのようなノーコードツールを活用すれば、プログラミング知識がなくても二段階抽選を簡単に実装できます。
柔軟な抽選設計が求められる場面では、ノーコードツール「キュリア」の活用を検討してみてください。
誰でも簡単に、思い通りの抽選コンテンツを作成・運用できる環境が整っています。
さらに、クラウド型サービスであるため、インターネット環境さえあれば、いつでもどこでも抽選システムの作成・管理が可能です。
また、仕様に変更があった際にも即座に対応できるため、キャンペーンやイベントの内容に応じて柔軟にシステムを調整することができ、外注費用を大幅に削減できます。
二段階抽選を活用して、参加者にとっても運営者にとっても満足度の高いキャンペーンを実現しましょう。